こんにちは、サボり癖日本トップ層のぐでまるです。
習慣になりかけていたのに、途中で全部サボった──。
あと少しで続けられたのに、なぜ止まっちゃうのか。
この記事をクリックしてくれた浮かれ仲間なら、心当たりがあるはずです。
頑張ってこいで勢いがついた自転車から、途中で降りてしまうもったいなさ。
僕も「もう少し続けていれば…」と今でも後悔しています。
でも大丈夫。小さな成功は悪くない。
問題は扱い方です。
浮かれ期でも止まらずに習慣を続けられる仕組みを作れば、成功の喜びを次のステップにつなげられます。
この記事では、僕の失敗体験とそこから学んだ「浮かれ期でも止まらない仕組み作り」を具体的にシェアします。
読むだけで、達成感を次の行動に変える具体的な仕組みが手に入ります。
小さな成功で浮かれて、その後サボった僕の失敗談
「続けるコツを掴んだ!」と思った瞬間、急にやる気が抜けてしまった経験、ありませんか?
達成感のあとに気が緩み、あっという間に元通り。
「あの時やめなきゃよかった」と後から気づくパターンです。
最初の数日間は順調でも、すぐに崩れた経験
僕は複数のブログを運営しています。
8年前に始めた最初のブログでは、なんとか月8万PVまで成長させることができました。
毎月お小遣い程度の収入も入ってきて、「まぁもういいや」と満足してしまったんです。
正直、ここまで伸ばすのに使った労力が大変すぎて、さらに次のステップに挑戦する気力が湧きませんでした。
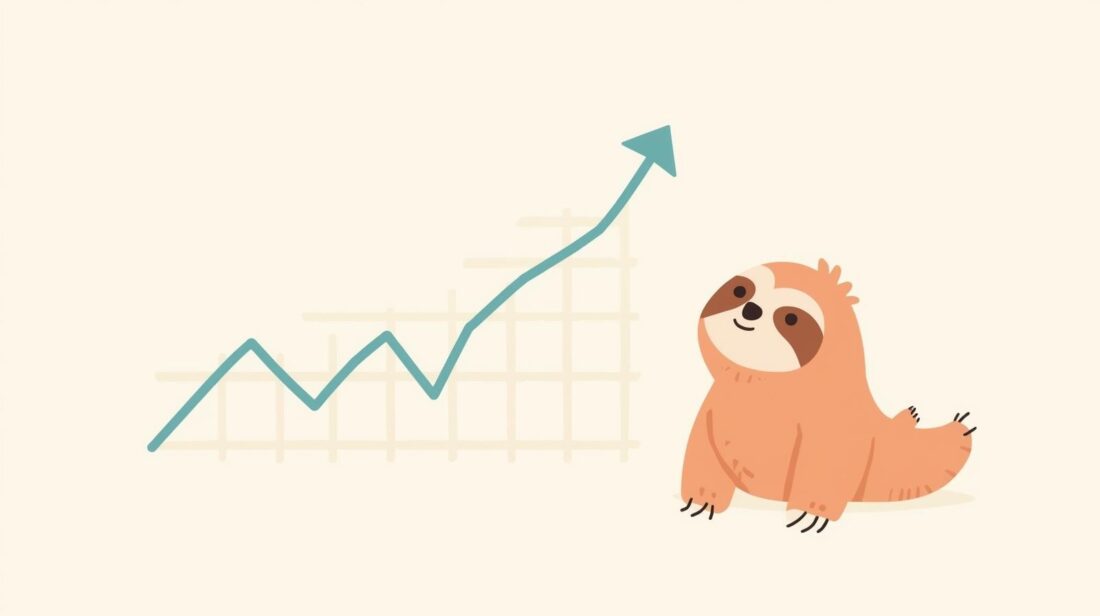
もし同じ時間と労力をかけて続けていれば、指数関数的に伸びたはず。
この達成感に浸ったあとの「止まり方」が、僕の大きな失敗談です。
「少しできた」→「休んでもいいか」→そのままフェードアウト
「少し続けられた」だけで満足してしまうと、心の中で“休んでもいい”の言い訳が生まれます。
その結果、習慣が自然にフェードアウトしてしまうのです。
“続けられた”と“続く状態ができた”の違いに気づいていなかった
ただ単に「続けられた」ことに満足してしまうと、習慣が定着した状態にはなりません。
成功の質を見誤ると、達成感が逆効果になってしまうのです。
達成感は悪くない、ただ“扱い方”を間違えると止まる
途中で止まってしまうのは、意志が弱いからではありません。
「ちょっと成果が出た」瞬間に気がゆるむのは、人間として自然な反応なんです。
小さな成功はうれしい。でも、扱い方を間違えると一気にブレーキになります。
ここからは、僕自身の失敗をもとに、「なぜ達成感で止まってしまうのか」を掘り下げてみます。
達成感を得て「もうゴールに到達した」と錯覚した
僕らは努力の手応えを感じた瞬間、つい「もう十分やった」と思ってしまいます。
途中なのに“ゴールした気分”になるんです。
気持ちが一度ゆるむと、次の行動に向かうエネルギーが出にくくなります。
「よし、やり切った!」と思った直後にサボりたくなるのは、そのせい。
僕も「PV8万いったし、もう頑張らなくていいか」と気を抜いてしまいました。
けれど、今思えばあの瞬間こそが“次のステップの始まり”だったんですよね。
小さな成功はブースターにもブレーキにもなる
小さな成功って、正しく使えば最高のブースターです。
でも、扱いを間違えるとブレーキにもなる。
僕がサボったときも、成功体験そのものが悪かったわけではなくて、
「成功=安心ゾーン」
に入ってしまったのが問題でした。
努力の緊張感がほどけて、気づけば「また明日でいいか」と思考が緩む。
この“油断スイッチ”こそが、習慣を止める最大のトリガーです。
成功=行動のエネルギー源。ただし「安心ゾーン」に入りすぎると停滞する
達成感は本来、次の行動への燃料です。
でも、それを“安心材料”として使ってしまうと、成長が止まります。
僕の場合は「8万PV」という実績が、「自分はもうできる人だ」という錯覚を作り、最小限は必要な【危機感を奪った】んです。
成功を「ご褒美」で終わらせるか、「スタートの合図」に変えるか。
ここが、“続ける人と止まる人”の分かれ道になります。
浮かれたまま止まるか、次のステップに活かすかで価値が変わる
小さな成功は、それ自体が悪いわけじゃありません。
問題は「浮かれた状態で止まるか」「次のステップに活かすか」。
同じ達成感でも、この選択で未来の伸び方がまったく変わります。
僕も「やっとできた!」の達成感に安心して、行動を止めてしまったときは、せっかくの勢いをゼロに戻していました。
でも、ほんの少し意識を変えるだけで、達成感を“ブレーキ”ではなく“燃料”にできるんです。
達成したら「休む」でも「終わり」でもなく、“次にやりやすくする仕組みを整える”ところまでが本当のゴール。
そこまでできれば、浮かれ期さえも「習慣が定着する加速タイム」に変えられます。
小さな成功を“終わり”ではなく“スタート”に変えるコツ
「うまくいった!」という瞬間ほど、次の一手が大事。
ここで止まるか進むかで、“続く人と止まる人”の差がつきます。
コツは、達成を“終わり”じゃなく“設計の途中”ととらえること。
僕がいろいろ試した中で、「浮かれ期でも止まらない仕組み」を作るのに効果的だったコツを3つ紹介します。
成功したら“祝う”より“仕組み化”する
うまくいった時ほど、気合いを入れるより「続けやすい形」に変えるのがポイントです。
たとえば、
- ちょっと面倒だった部分を減らす
- 開始までのハードルを1手減らす
- 「ここまでは自動でやる」と決める
僕の場合、【スタートの手間を減らすこと】が継続できる鍵でした。
「次も自然に動けるように」環境や流れを少しずつ整えています。
・ブログなら、翌日にすぐ書けるように下書きのタイトルだけ残しておく
・朝の作業なら、使うタブを開いたままPCを閉じる
・掃除なら、道具を“やる場所”の近くに置く
こうした“小さな整え方”が、結果的に仕組み化になります。
気合いも分析もいらず、自然に「続けるループ」に入りやすくなるんです。
翌日のハードルを「ちょっと物足りない」くらいに設定
達成した翌日ほど、気が緩んで止まりやすい。
そんな時に有効なのが、“あえて未完で終える”やり方です。
「あと少しできそう」でやめておくと、脳が「続きが気になる」状態を保てる。
この“未完バトン”が、次の日の行動スイッチになります。
完璧にやりきるより、「ちょっとだけ物足りない」で止める方が、継続のリズムが生まれるんです。
喜びを「次の行動」にすぐつなげるループ設計
達成感を感じたら、その勢いのまま“次の行動”に小さくつなげる。
たとえば、
- 翌日のタスクをメモしておく
- 作業環境を整えておく
- 「次はここからやる」と一言残しておく
こうした“次に動きやすくする仕掛け”を残しておくことで、喜びのエネルギーを行動の燃料としてリレーできます。
「できた!」で終わらせず、「次もできそう!」につなげることが、続く人の共通点です。
まとめ|“気づけば動ける人”になるために
「続けよう」と思っても、途中で止まるのは意志の弱さではありません。
脳が達成感で“もう十分”と錯覚して、省エネモードに入っているだけです。
重要なのは、浮かれた後でも自然に動ける仕組みを作ること。
僕がこの記事で紹介したコツをまとめると、次の3点に集約できます。
- 勢いを残す仕組みを作る
→ 翌日のハードルを少し低くして、最初の一歩をスムーズにする。 - 成功を次に活かせる形に整える
→ 小さな成功の後も、自然に次の行動に移れる環境や流れを作る。 - 仕組みで淡々と回す
→ 気分やテンションに頼らず、毎日少しずつ動ける仕組みを残すことで、行動を習慣化する。
小さな成功は、“やめるきっかけ”ではなく、“続ける燃料”に変えられます。
勢いに任せるのではなく、ちょっとした工夫と仕組みで次の行動につなげれば、浮かれ期さえも習慣を定着させる力になります。


